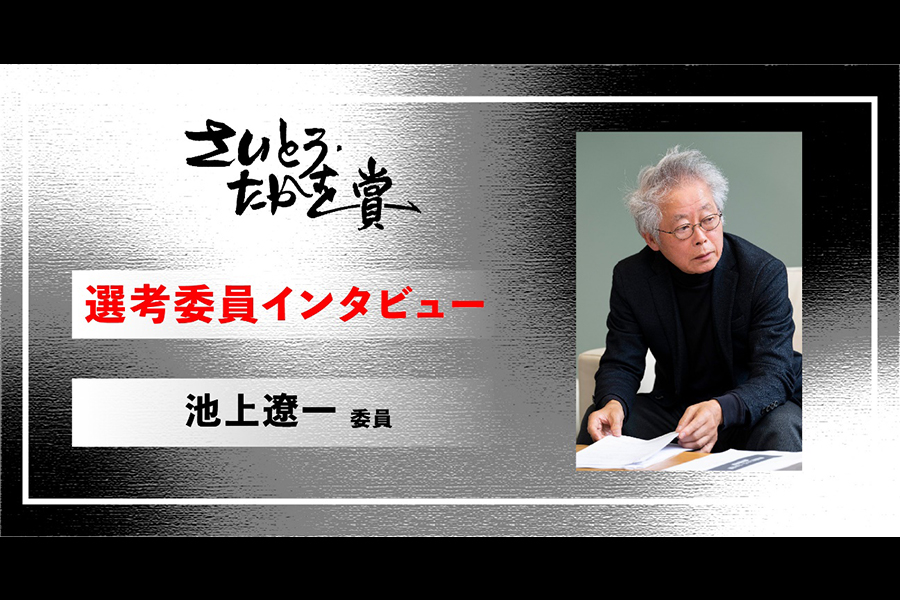
さいとう・たかを賞 選考委員インタビュー 池上遼一委員
第1回さいとう・たかを賞から最終選考会選考委員を務めていただき、ご自身も『サンクチュアリ』や『トリリオンゲーム』で作画を手掛ける劇画家の池上遼一委員に、賞の意義や作画家の心得をお聞きしました。
――さいとう・たかを賞の意義はどこにあると思われますか
最近マンガのレベルがどんどん上がってきていると思います。今後さらに新しいものが出てくるんじゃないでしょうか。同じ時代物でも、全く違う角度で書かれた作品が出てくることを期待しています。僕はハードボイルド的なものも好きなんだけど、それもまた違った視点で描いてくれると嬉しいなと思います。
僕個人としてはまださいとう・たかを賞の名にふさわしい作品があまり出てきていないなと感じています。「さいとう・たかを」という冠がある限り、やはりさいとう先生の世界観をちょっと違った視点で描けるような人が出てきてほしいですね。
映画監督のクエンティン・タランティーノさんは、昔の西部劇とかを新しく作り変えるんですよね。古いものを見つけてまた違った目で見ると新しいものができるぞみたいな、そういう作り方しているんです。今の若い漫画家も昔のマンガを否定しないで読んでみると、その良さが見つかると思うんですよね。
――さいとう・たかを賞だからこそ、どの作品を選ぶべきかいう視点はありますよね
小説でいえば、江戸川乱歩賞とか、大藪春彦賞とか、賞の名前によって受賞する作品の性カテゴリーが決まってくると思っていました。でも他の選考委員の方々がそれでは狭すぎるんじゃないかと……。読者が求めているのは常に変わるじゃないですが、日常の生活の中で、人と人の繋がりとか、そういうちっちゃい感動をすごく面白おかしく見せるものもやっぱり認めたほうがいいんじゃないかっていう意見があり、みんな悩みましたね。
例えば第3回さいとう・たかを賞最終候補作の『ましろ日』は、地味な話なんですけど、ものすごく綺麗に描いているんですよね。盲目の走者だから、逆に光をものすごく丁寧に演出しているんです。太陽の光とか、キラキラした海に反射する光とかね。素晴らしいなと思って、僕も上位に入れたんです。
――選考ではどのようなところを評価されるのでしょうか
僕以外の原作者の目を持った選考委員の方は、キャラクターとかストーリーを中心に評価の対象としています。原作の面白さは大事なんですけど、そのストーリーと画描きがうまくマッチしてないとヒットに結びつかないんです。でも最終選考会に残った4~5本の作品はどれも遜色ないんですよ。少年誌とか青年誌とか、いろんな雑誌がありますが、発表の場によって面白さが変わってくるので評価が本当に難しいんですよ。
―-講評のときに、作品が時代性を表しているかどうかとおっしゃっていましたね
僕は、いつも選考するにあたって、構成とか、お話がよくできているということは、今の時代を描いているかというところに一番視点を置いています。皆さんそれぞれ違った視点で作品を見られていますが、それはそれでいいんじゃないかと思っています。何人かで評価するというのはそういうものだと思います。
――作画を見るときに、どのような点で評価されているのでしょうか
僕の持論として、マンガにとって画っていうのは小説に例えれば文体みたいなもんだと思っています。だからストーリーとかテーマ性によって、どんな画柄でもマッチしていればいいんですよ。さいとう先生の画でメロドラマやっても全然駄目じゃない。ヒットする作品はストーリーと画が合っていますよね。
一方、ピタッと合ってないとちぐはぐなイメージを抱いてしまいます。違和感のみが残ってしまう。今の『鬼滅の刃』もそうだけど、違う作家の絵でやっていたらギャグシーンで笑えなかったりとか。歌詞と同じで、同じ歌詞を、違う人が歌ったら大ヒットしたっていうのがよくあるじゃないですか。原作付きってのはね、画の上手い下手じゃないんですよ。
――テーマに画が合っているかどうかということですか
原作が訴えるものを読解するリテラシーがしっかりしてないと作画家としてはだめですね。単に画がうまいだけの画描きさんでは原作付きマンガの作画をこなせないんですよ。おそらく演出も考えつかないと思うんです。ここは「ぱーん」と大きくしたいとか心情面のところを見開きにするとかね。
雁屋哲先生と組んだ『男組』は、アクションシーンで大きいコマをバンバン出していたんですよ。ところが後半になって、主人公の目が一時的に見えなくなってライバルとすれ違うシーンを見開きで書いた。それがすごく印象に残っているって、後で聞きました。だからアクションを大きく取ってもやっぱり駄目だなと思った。脚本を読んで、ここに原作者が力点を置いているというのを察知する能力がないと、作画は駄目なんじゃないかな。
どこを切ってどう見せるかっていうコマ割りが重要なんですよ。脚本の通りにやれっていう原作者の方と、適当に端折っていいよっていう人がいるんですが、やっぱり画描きの力で「ここはこう端折っていいな」とか見極める感性だと思うんですよね。
小説をマンガにする場合もそうだと思うんですけど、映画を作る感覚と同じ作業が必要なんです。どこをどう見せるのかという演出のところが重要になる、全部を入れたら到底入らないですからね。
――現在連載中の『トリリオンゲーム』では、稲垣理一郎先生と組まれました
これはね、僕が今まで書いたことがないようなものになっていると思うんですよ。この歳でちょっと絵柄も変えてきているし。脚本自体が、ネーム原作という、構成と簡単な下絵まで描かれたものです。最初は正直ネーム原作にちょっと抵抗感ありました。悩んだんですけど、読んでみると、今まで僕が培ってきたようなコマの割り方とは全く違って、ギャグなんかも今のセンスがあるでしょう。だからこれは勉強になるんじゃないかなと思ってやることにしたんです。
だからギャグの部分はもう稲垣先生のネームに忠実にやっています。それ以外は、僕の絵柄を多少微調整して。稲垣先生の世界観に近づけるために、ちょっと幼くしたりとか、今風に変えてきている。これ『男組』のときの絵だったら駄目ですよ。
担当者の「これ、化学反応起こすから」っていう通りになってきました。活字の脚本ではちょっとできないですね。なぜかというと、僕がITに全然詳しくないから。稲垣先生自身は、コンピューターに詳しいし、さらに専門の会社の人たちの協力を得て、作中のパソコンの画面作りは向こうから指示してもらっているんですよ。
この作品を始める前は相当ジレンマがありました。今まで、活字の脚本でいただいたら、それを自分なりに内容を理解して、演出を考えてコマ割りをして下書きをして仕上げたわけでしょ。それが下書きまで入ってきているわけですよ。そうすると、単なる絵描きになるんじゃないのかなっていうね。
原作の方は若いんですよね。だから、もう勉強させてもらっているつもり。すごく教えられることがいっぱいあるんですよ。ギャグのやり方とか。ちゃんと笑わせるために巧妙な伏線が張ってあるんです。小池一夫先生と初めて仕事させてもらったときのようなトキメキがあります。
小池先生は「劇画っていうのはこういうふうにコマ割ってこういうふうに構成するんだ。演出はこうなんだ」と、いちいち書いてくるんですよね。僕はそれ以前にガロとかそういうところで描いていましたので、読者のことなんか全く考えてなかった。自分の内面を好きなように書いていたので、エンターテイメント性を教えられたのが小池先生だったんですよ。その時と同じような高揚感がある。
――そうしたところは分業ならではの魅力ですね
画的には僕のかっこいいキャラが欲しいんですよ。でも小池一夫先生や武論尊先生と組んでいた時の通りにやったんではもう今の時代は受け入れられない……。稲垣先生の今回の『トリリオンゲーム』はチャラいキャラクターでいい男前ってなっているからそれに合った顔立ちにしようと努力しています。
『トリリオンゲーム』の連載が実現したのは、この企画を考えた担当者のおかげですね。担当者が思い描いたように化学反応が起こり、違和感なく読者に受けられている。僕が嬉しかったのは、これまでの作品までは、読者層が60歳から70歳くらいでしたが『トリリオンゲーム』は僕の下の孫の、中学3年生も「おじいちゃん面白いよこれ」って言ってくれるんですよね。僕の画なんかしらない世代が画柄をちょっと変えただけで違和感を持たなくなっているんですよ。そういう意味では、ストーリーにピタっとあった画さえあれば、どんな画だっていいんだなと思う。
――分業制をうまく成立させるには担当者の熱量も必要なのでしょうか。
どの原作者の脚本とどの画描きと結びつけるかっていうのは編集者の腕じゃないですかね。プロデューサーとしての目がないとだめじゃないのかな。僕が雁屋先生と組んだ『男組』のときにギャグ風の絵で遊んでいるところもあるんですよ。だから「稲垣先生と組ませればこういう絵も描ける」っていうようなのもあったんじゃないですか。がっかりする人もいるだろうし、面白がってくれるひともいるだろうし。賭けだから、蓋開けるまでわからないから。
――その点では『ゴルゴ13』は安定しています
『ゴルゴ13』の素晴らしいところは、まず強烈なキャラクターの存在が大きい。次に原作者が複数いることですね。1人や2人の原作だったらこれだけ長く続かないでしょう。脚本家としては未成熟でも専門的知識を持った人たちとかに描かせているわけでしょ。それを構成して消化する能力がさいとう先生、さいとう・プロダクションにあったから長く続いているわけですよね。今更ながら、分業システムを実践されて走られたさいとう先生に敬意を表します。今後、さいとう・たかを賞が長く続くようにと願っています。
インタビュー:松尾奈々絵
執筆:いわもとたかこ
編集:山内康裕
